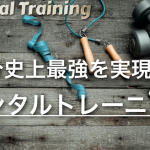メンタルタフネスとは、
プレッシャーがかかる中でも理想的な状態で必要なことに集中できる力
のことをいいます。
人生では、プレッシャーのかかることが多くあります。
・仕事のノルマに対するプレッシャー
・お金を稼がなければならないというプレッシャー
・本番で力を発揮しなければならないというプレッシャー
・試験で結果を出さなければならないプレッシャー
それらのプレッシャーがある中でも、僕らは日々を生きる必要があり、結果を出す必要がある。
それってなかなかに大変ですし、心身も疲弊しますよね。
メンタルタフネスは、そのようなプレッシャーがある状況の中でも【理想的な状態】で在れる力のこと。
この記事では、そんなメンタルタフネスをどのように身につければいいのか?について解説していきます。
【記事を書いている人→ 池田潤 コーチ・メンタルトレーナー。20代で6万5千部のベストセラー含む5冊の本を出版(自分の武器を見つける技術、無愛想のススメなど)。900名以上が参加した心を鍛え整えるジム「イケジム」を運営。コーチ・トレーナーとして心の状態&パフォーマンスを最大化するサービスを提供。京大法学部合格後、ブログを書き始め、今に至る。趣味は、筋トレやボドゲ、読書。毎朝起きてカフェに行くのが日課】
タフなメンタルの身につけ方
結論から言えば、
『ほんの少しずつストレスに身を晒し、十分な回復を取る。その往復運動を繰り返すこと』
になります。
「え!ストレスに身を晒してしまったら、メンタルがやられてしまって、タフになるどころかよわっちいメンタルになるのではないですか?」
と思いますよね。僕もそう思っていました。
しかし、最新の研究によってそうではないことが分かっています。
むしろ、『ほんの少しずつ』ストレスに身を晒すことによって、
そして十分な回復期間を取ることによって、メンタルはタフになっていくのです。
そのことを示す本や事例を紹介しましょう。
『メンタルタフネス ストレスで強くなる ジム・レーヤー CCCメディアハウス』
からの引用です。
====================
常識1 ストレスは良くない。できるだけ避けるべきだ
常識2 ストレスがなくなれば、幸せになれる
常識3 ストレスは健康に悪い
常識4 ストレスが少ないほど、生産性が上がる
常識5 ストレスをうまく処理できなければ、出世コースから脱落する
常識6 ストレスに強いかどうかは生まれつきの問題だ
常識7 ストレスが大きいほど、不幸になっていく
常識8 年をとるほど、ストレスを避けるようにした方がいい
常識9 ストレスにさらされていると、身も心もボロボロになる
常識10 ストレスの大きさは、自分の身にどれだけ悪いことが起きたかで決まる
こうした「常識」はすべて間違っている。
本書では、私がこれまでの経験と研究から得た結果を生かし、ストレスについての全く新しい常識を提示していきたい。
それは、
ストレスは(肉体的なもの、精神的、感情的なもの、何であれ)あなたのためになる
ということだ。
〜中略〜
人間というのは、最もストレスを受けた部分が最も成長するものだ。
「ストレスにさらされること」で、より大きなストレスにも耐えられるようになるのである。
タフであるというのはリラックスして、必要なことに集中できる状態を意味する。この状態を私は「理想的な心理状態(IPS)」と呼んでいる。
真のタフネスが身についているかどうかは、しっかりと回復ができる訓練をしたかどうかにかかっていたのだ。
最高のパフォーマンスを引き出すには、選手の生活すべての面において、このバランスを保つことが必要なのだ。
この事実を発見したことで、われわれの研究は大きく進歩することになった。
=======================
以下、「不老長寿メソッド 鈴木祐 かんき出版」という書籍からの引用です。
=======================
「私を滅ぼすに至らないすべてのことが、私を強くする」
この言葉は、ドイツの哲学者ニーチェが、人間が持つ回復力のメカニズムを端的に表現したものです。
「10代の部活で先輩に怒鳴られて忍耐力がついた」や「仕事で味わった苦労が転職に役立った」といった経験は誰にでもあるはず。
パワハラのように理不尽な苦労は論外ですが、「適度な苦痛」が私たちの能力を高める力を持つのは間違いないでしょう。
「ハードに訓練せよ。しかし、それ以上にハードに休憩せよ」
という格言が、アスリートの世界にはあります。
体を鍛えるには厳しいトレーニングが欠かせないが、それ以上に「回復」のフェーズが重要だという経験則を言い表した言葉です。
いかにアンチエンジングには「苦痛」が不可欠だといっても、常にストレスを抱えていたら心身が病むばかりでしょう。
「苦痛」を若返りの源に変えるには、回復のフェースが欠かせません。
筋肉の成長が良い例です。
ご存知の通り、筋肉量を増やすためには、トレーニングで筋繊維を傷つけたあとの適切な休憩と栄養補給が必須。
休憩をはさまずに運動を続ければ筋繊維を修復する時間が得られず、ほどなく限界に達した肉体は、さまざまなレベルの不調を訴え始めます。
不老長寿メソッド 鈴木祐 かんき出版
====================
オーバートレーニングとアンダートレーニング
私たちのメンタルタフネスが低下するときは、
・十分な消費ができていないとき(アンダートレーニング)
・十分な回復ができていないとき(オーバートレーニング)
です。
アンダートレーニングの状態とは、例えばコミュニケーションで考えると分かりやすくなります。
コミュニケーションを取る回数が少なくなると、十分な消費活動が行われず、アンダートレーニングの状態になります。
すると、コミュニケーション時に緊張したり、不安になったりして、プレッシャーを感じ良い状態でいられなくなります。
異性との関係でも同じで、異性と会話する機会が少ない(アンダートレーニング)状態になると、コミュニケーション時にプレッシャーが高まります。
そのプレッシャーの中で緊張してしまい、理想的な状態でいられなくなってしまうんですね。
それはすなわち、消費活動が少ないことによる状態の低下です。
こういう場合、小さく消費活動を行う(コミュニケーションの経験を積む)ことによって状態は改善していきます。
アンダートレーニングだった分野の行動量を少しずつ増やしていく。
その際、もちろんプレッシャーや不安、心配は出てくるのですが、それで良いのです。
あまりに大きなプレッシャーは良くありませんが、小さなプレッシャーに自分を晒していくことによって、だんだんとプレッシャーに慣れてきます。
慣れると、緊張も不安も感じることなく、自然体でコミュニケーションが取れるようになっていきます。
アンダートレーニング状態の分野の場合は、少しずつプレッシャーに身を晒す練習をしていくことによって、メンタルタフネスを鍛えることが可能です。
回復の時間を取ることでタフなメンタルは身につく
一方、回復不足が原因でメンタルタフネスが低下している場合もあります。
心と体が疲れている、疲弊していることによって、タフネスさが失われているケースです。
例えば、仕事のプレッシャーに長期間晒され、心理面で負担がかかっているにも関わらず、リフレッシュしたり、休む時間がない。
すると、脳は疲労し、心身も常に張り詰めている状態に。
結果、メンタルタフネスが低下し、プレッシャーがかかったときに状態が著しく低下してしまうのです。
消費不足も良くないですが、回復不足もメンタルタフネスを低下させます。
回復不足の場合は、
・栄養補給
・リラックスする時間
・瞑想
・ストレッチなどで体を緩める
・明るくポジティブな感情を感じる時間
・純粋に楽しめることに打ち込む時間
・十分な睡眠時間
を確保します。
上記の時間を確保することに抵抗を感じたり、回復の時間を過ごすことを許可できないこともあるのですが、
回復の時間を取れば、むしろパフォーマンスは上がります。
回復の時間がないことによって本来のパフォーマンスを発揮できず苦しんでいる状態なので、
回復の時間はむしろ自分のパフォーマンスを上げてくれる。
そう理解することが低下感を減らすことにつながります。
大事なのは、自分自身の状態や状況を理解すること。
自分は今、アンダートレーニング状態なのか、それともオーバートレーニング状態なのか。
そこを理解することによって、メンタルタフネスを高めるための具体的な方法が見えてきます。
次に、メンタルタフネスを高めるための消費活動についてですが、
ほんの少しの負荷からスタートすることが重要です。
大きすぎる負荷だと、そもそも取り組むことができず、消費活動をスタートすることができません。
これから初めて筋トレをしようというときに、いきなりベンチプレス100キロから始めようとすれば、
持ち上がらないですし、怪我をする可能性もありますよね。
ですが、10キロであればなんとかなるかもしれません。
10キロであっても筋肉を使うことができれば、着実に筋肉は成長する方向に進みます。
メンタルでも全く同じで、いきなりハードルを上げすぎて全く消費活動ができないよりも、
ほんの少しでもいいので消費活動をする方が、メンタルタフネスは鍛えられていきます。
例えば、コミュニケーションでのプレッシャーに対処する力について言えば、
・好きではない異性と話す(好きな異性よりもハードルが低い)
・自分から積極的に人を誘ってみる
・自分から挨拶する
・相手の良いところを自分から伝えてみる
・知らない人に話しかける
・上司に自分から話しかける
・新しいコミュニティに参加する
・初対面の人と話す
などになります。
上記の例はあくまでも例であり、大事なのは「あなたがほんの少しハードルを感じること」を設定することです。
このハードルが高すぎると効果的なタフネストレーニングは難しくなります。
「ハードルをいかに下げるか」
これがキーになっていて、ハードルを下げられれば下げられるほど、うまくいきます。
なぜなら、ハードルを下げられればこそ、実践実行ができるからです。
実践実行ができれば、タフネストレーニングを積み重ねていることになるので、着実にタフネスは身についていきます。
僕らはどうしても「ここまでやらないとダメだ」と感じすぎてハードルを上げてしまい、結果的にタフネスを身に付けられないでいます。
ほんの少しでもいいので実践していけることがメンタルタフネスを鍛えることになり、
プレッシャーや緊張に負けない自分を作ることになっていくことをぜひ覚えておいてください。
本番へのプレッシャーに対処する力で言えば、
・時間制限を少し厳しくする
・本番を想定して取り組む
・より厳しい環境で取り組んでみる
・誰かと競う状況にするなどのプレッシャーをあえてかける
・遊びで、「うまくできなければ罰ゲーム」などのプレッシャーをかける
・「うまくできれば報酬を得られる」などのプレッシャーをかける
・誰かに見ておいてもらうというプレッシャーをかける
などになります。
最も良いのは、本番以上に強いプレッシャーをあえて自分にかけて、本番の方が楽である状況を作ることです。
「本番が一番キツイ」ということだと、うまくいきません。
それは練習不足トレーニング不足で、本番よりも厳しい状況、キツイ環境、タフな条件で日々練習することが大切です。
練習段階で、最低でも本番と同等、できればそれ以上の状況・環境・条件を作ってトレーニングしておくこと。
そのような【消費活動】を普段から行っておくことによってメンタルタフネスは向上し、
本番でのプレッシャーが減り、理想的な状態でいられるようになっていきます。
例えば、僕の場合で言えば、受験時代、センター試験や二次試験のプレッシャーに対処するため、
・うるさいファミレスで過去問を解く
・その中でも特にうるさいお客さんの隣にあえて座って過去問を解く
・時間制限を試験本番よりも短くする
・試験本番よりも短い時間で合格点を取れる実力をつける
・試験本番よりも難しい問題を解ける実力をつけておく
という風にしていました。
そうやって本番よりも厳しい状況で練習しておくことによって、本番のプレッシャーにも対処できるタフネスが身につき、
自分の力を発揮することができて、試験に合格することができました。
まとめ
メンタルタフネスを鍛える方法をまとめると、重要なのは、
『ほんの少しずつストレスに身を晒し、十分な回復を取る。その往復運動を繰り返すこと』
です。
小さく心身を消費し、十分な回復時間を取る。
その両方が大事で、その往復運動を繰り返していくことでメンタルタフネスは高まっていきます。
ぜひあなたがタフネスを高めたいと思う分野について、消費と回復の往復運動を実行してみてください。
無料メールトレーニング講座を提供しています。
このメール講座だけで、
・本物の『自信』を持つ方法
・『メンタル』を強く安定させる方法
・『人間関係』を楽にする秘訣
・関係性を良くする『コミュニケーション』
・状態を整える『認知』の仕方
・自分で自分の『心の状態』を整える
・『行動力』を無理なく上げる方法
など、あらゆる分野を学んでいただけます。メンタルの基礎から応用まで網羅しており、これさえ受講いただければ、という内容になっているので、ぜひお受け取りください。完全無料で、いつでも簡単に解除できます。
あなたに本当に必要な一歩を知れる【体験トレーニング】を実施しています。詳細は下記からご確認ください↓
LINE@でも最新情報、LINE限定コンテンツを随時配信中です。
YouTubeもやっています。
noteも書いています。
:note文章版メンタルトレーニング「自信を鍛えるメントレ」
本も出版しています。
こちら韓国でも出版されました。
「無愛想のススメ〜人間関係が劇的に改善する唯一の方法〜(光文社)」 発売4日で増刷!