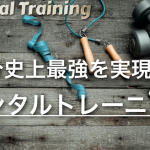この記事では、人に嫌われるのが怖い…状態をどうやって改善するか?を解説します。
僕は16年間メンタルトレーナーをしてきました。その間、この相談はたくさん受けてきて、実際に解決に導いてきました。
その際に使った手法について、論文や研究も参考にしながら、担当したトレーニングの経験も踏まえて解説していきます。
【執筆・監修:池田潤(コーチ/メンタルトレーナー) 16年間で1万人以上の相談実績を持ち、メンタル専門ジム10年運営で1000名以上が受講。6万5千部のベストセラーを含む5冊の著書を出版。科学的根拠に基づいた「今日からできるメンタル強化」を専門としています。 詳しいプロフィールはこちら 】
脳は『過剰な不安』を作り出す
嫌われることが怖いとき、一つの大事な観点は、
脳が感じる恐怖は『過剰』であることが多い
という点です。
つまり、必要以上に嫌われることを怖がりすぎている可能性があるということ。ここに一旦目を向けてみましょう。
・実は嫌われることはそこまで怖いことではない
・実は嫌われることはそこまで起こらない
という2点が大事です。
人から極端に嫌われることは頻繁に起こるわけではありません。
たくさんの人がいる中で何人かに嫌われることは誰にでもあり得ることです。
まずは自分が感じている「嫌われる恐怖」が『過剰』になっていないかどうか。
ここを整理していきましょう。
脳は【生存】を目的に活動しています。
だからこそ、生存に少しでも関係することには過剰に反応します。
人間社会においては、「他者に嫌われること」は原始時代は生死に関わることでもありました。
なので、DNAレベルで過剰に敏感に反応するようにできてます。
さらに、もしも親が不機嫌なことが多かったり、周囲のパワーを持っている人の機嫌が重要だった経験がある場合。
DNAレベルでの過剰さに加えて、経験レベルでの過剰さも上乗せ。
経験レベルでの過剰さとは、例えば、親の機嫌がどうだったか。
親の機嫌は子供にとって重要なものです。
子供は自分ではご飯を食べられませんし、お金を稼げるわけでもありません。
自分の生存にとって親に気に入られることはすごく大事です。
だからこそ、親の機嫌に敏感になります。
自分のどんな行動が親を機嫌良くして、どんな行動が親を不機嫌にするのか。
そのことにしっかりと「敏感」になることによって、生存できるように頑張ってきた。
そういう経験がある場合、高校、大学、大人になっても『敏感さ』を持つケースがよくあります。
その敏感さこそが『過剰さ』に当たるわけですね。
これは僕自身もまさにそうで、僕の脳も昔は過剰な反応を示していました。
他者の表情や雰囲気から機嫌を察知し、機嫌が悪い人がいたら自分が何とかしなければならないと思っていました。
無意識のうちにそう感じてしまうわけです。
それがストレスで、人と一緒にいると疲れてしまう。家に着くとぐったり疲れる。そんな状態でした。
いつも気を張っているというか、無意識に周囲に気を配っている。神経が張り詰める。
結果、脳が疲れてしまう。
そんな僕でしたが、この記事に書いていることを実践。すると、今ではそういったことが全くと言って良いほどなくなりました。
メタ認知で嫌われる恐怖は軽減できる
そうやって過剰さを整えることができたのには、一つの理由があります。
【メタ認知】という言葉を聞いたことはあるでしょうか?
【自分の認知を認知する】ことを言います。
メタ認知ができると、感情のコントロール力が上がることが研究でわかってます。
人に嫌われる恐怖に関して言えば、メタ認知を活用できれば嫌われる恐怖を軽減できるということです。
では、メタ認知はどうやって実践すればいいの?となりますよね。それがまさに、
恐怖の過剰さに気づくこと
に他なりません。
「自分はこれまで、こういう経験をしてきたから、嫌われることに過剰な恐怖心や不安感を感じてしまうんだな。
でも、これは『過剰』であって、そんなに恐れることはないし、実際に嫌われることが起こるわけでもないのかも」
という風に考えていくということ。
その上で、例えば、「嫌われたのでは?」と感じた人に自分からアクションを起こしてみる。
ひょんなことからコミュニケーションを取ることになる。
すると、
「あ、本当に大丈夫だった」
という経験を積むことができたりする。
そうなれば、「やっぱり自分の恐怖は過剰なものだったんだな」と気づくことができます。
認知行動療法的アプローチで恐怖を減らす
これは認知行動療法と呼ばれる手法でもあります。
認知行動療法のイメージは、
無理に考え方を矯正するのではなく、自分の考えが構築されるきっかけになった今までの経験に向き合うことで、異なる視点もあることに気づくこと。そして、個人個人の認知をよりネガティブなバイアスの少ないものへと変えていくイメージです。
REAPPRAISAL 内田舞(ハーバード大学医学部准教授)実業之日本社
です。
いきなり無理に考え方を変えようとするのではなく、ただ自分の認知を認識し、客観的にみられるようになっていきます。
すると、他の見方に対して心が開かれるようになり、
「自分はこういう見方を経験上してしまうけど、本当は違う見方をしてもいいのかもしれない」
と感じられるようになっていきます。
認知の歪みを修正することで恐怖を減らす
さらに具体的に、人間関係における『認知の歪み』について扱っていきます。
僕はメンタルジムというメンタル専門のジムを運営しているのですが、そこで大きなテーマとして扱うのが、
タテの関係とヨコの関係
という概念です。
人に嫌われるのが怖い場合、無意識的にタテの関係の意識が強くなりすぎていることが非常によくあります。
相手は上で、自分は下という関係性の捉え方ですね。
「自分は下である」というイメージが無意識に活性化することで、
「相手は自分を評価する立場にある者であり、自分は評価される側の人間である」
と感じてしまう。
本来、人と人はヨコの関係で、誰もが同じ価値を持っています。
自分自身は誰かに評価される立場の人間であるというわけではありません。
自分が他者を評価してもいいのです。
しかし、なかなかそうは思えない。
他者との関係性を構築するときに、どうしても下の立場に入ってしまう。
嫌われることが怖いとき、そんな状態になっていることがよくあります。
解決策としてはここもメタ認知が重要。
まずは「自分が無意識に自分を下の立場に置いてしまっていないか」をチェックしていきます。
過去の人間関係、現在の人間関係を振り返り、下の立場に入ってしまっている場面を思い出し、分析。
その上で、イメージの中で「ヨコの関係で接している自分」について考えていきます。
イメージトレーニングはメンタルを変えていく上で非常に有効なトレーニング法です。
イメージの中では失敗のリスクがないため、何度でも実践ができること。
さらに、脳は現実とイメージの区別がついていない。だから、イメージの中で実践したことであっても、しっかりと脳の神経回路に変化を起こしてくれる。
この2点から【最強のメンタルトレーニング法】と呼ぶことができます。
僕自身もタテの関係の下の立場に入ってしまうことはよくあったのですが、
① タテの関係の下の立場に入っている場面を特定
② その同じ場面で、もしヨコの関係の意識を持っているならどう振る舞うか?をイメージする
③ 態度、表情、言動、感情状態など、細部に至るまで何度もイメージする
④ イメージの中で何度も成功体験を積む
⑤ 実際に現場で少しずつ実践し、現場における成功体験を積む
という風にしてトレーニングを進めていきました。
すると、無意識にタテの関係の下の立場に自分を置いてしまう癖がどんどん改善。
ヨコの意識で人と接することが当たり前になっていきました。
感覚的に相手と対等でいられることによって、
「自分も相手のことを評価していいし、自分も相手を嫌いになっても構わない。自分は嫌われる側というよりも、好きになったり嫌いになったりする側である」
「相手だって自分と同じように嫌われることを怖がっている。そういう意味でも対等だ。自分だけが怖いわけではない」
「相手も自分との人間関係がこじれることは怖いはずだ。それだけ自分にも存在価値がある。自分だけが気を遣ったり、気にしすぎる必要はない」
という風に感じられる状態になりました。
上記の感覚がまさに「嫌われることを恐れていないときの感覚」になります。
価値ごとにしない力が嫌われる恐怖を減らす
次に、嫌われることを恐れているときのメンタルの特徴は、
相手の評価を自分の価値ごとにしている
ということです。
自分の価値ごとにするとは僕は作った言葉で、このブログでは頻繁に登場する概念になります。
自分の価値ごとにするとは、
本来は自分の価値とは関係のないものを『自分の価値と同一視する』『一体化して考えてしまう』
ということです。
今回で言えば、他者の評価が下がると自分の価値も下がり、他者の評価が上がると自分の価値も上がるように感じる。ということですね。
その連動性、同一視をゆるめていくことが自分の価値ごとにしないトレーニング。
嫌われることを恐れないメンタルの構築につながります。
相手が自分を評価してくれないと、自分には価値がないと『感じる』。
ただ実際には、自分をどう評価するかは相手の主観の問題です。
例えば、すごく良い人であれば自分のことをポジティブに見てくれるでしょう。
一方、ネガティブな人なら自分の悪い部分を見てネガティブに評価するかもしれません。
自分は全く変わっていないのに、人によってそれだけ評価が変わります。
ということは、人の評価とは自分の問題ではなく、
あくまでも「相手の主観がどうであるか」の反映だということになります。
このように相手の評価と自分の価値を関連づけなくなると、
相手が自分を好きかどうか、嫌いかどうかがあまり重要なことではなくなってきます。
「相手の評価はコントロールできないから、気にしても仕方ないよね。自分にできるのは、ただ自分らしくあることだけだ」
と達観する感覚になり、自分らしく自然体でいる能力も上がります。
価値ごとにしないことについてもメタ認知が重要で、
・価値ごとにしている場面を特定
・価値ごとにしていないとすれば、どう考え、どう振る舞い、どう感じるかをイメージする
ことを繰り返していきます。
最初の頃は、そうは言ってもやっぱり価値ごとにしてしまった、というところから始まります。
それで全く問題ありません。
同じように、価値ごとにしてしまった場面を特定し、そのとき、価値ごとにしないとすれば、どんな考え方や感じ方があったのか?を明確にしていきます。
そして、また現場で実践できるよう試していきます。
できなければ、【分析】と【イメージトレーニング】。
この取り組みを続けていくことで、価値ごとにしないことはどんどん上達していきます。
うまくできなかったことも全てはデータになりますし、新しいあり方をイメージトレーニングする機会にもなります。
なので、失敗やうまくいかないことを恐れることなく、取り組んでみていただければと思います。
そうすれば、次第に他者から嫌われることを恐れなくなっていくはずです。
30分間の無料体験オンライントレーニング、直接ご相談が可能です。興味ある方は下記から詳細をご確認ください。
:【30分で解決策を提供】オンライン無料体験パーソナルトレーニングはこちら
無料メールトレーニング講座を提供しています。
このメール講座だけで、
・本物の『自信』を持つ方法
・『メンタル』を強く安定させる方法
・『人間関係』を楽にする秘訣
・関係性を良くする『コミュニケーション』
・状態を整える『認知』の仕方
・自分で自分の『心の状態』を整える
・『行動力』を無理なく上げる方法
など、あらゆる分野を学んでいただけます。メンタルの基礎から応用まで網羅しており、これさえ受講いただければ、という内容になっているので、ぜひお受け取りください。完全無料で、いつでも簡単に解除できます。
:【より本格的にメンタルを学べる】無料メールトレーニング講座はこちら
LINE@でも最新情報、LINE限定コンテンツを随時配信中です。
【この記事を書いた人:池田 潤(いけだ じゅん) メンタルトレーナー / 著者 / パーソナルコーチ 1988年生まれ 16年にわたりプロアスリート、経営者、医療カウンセラーなど1万人以上のメンタルサポートに従事。著書5冊(累計10万部超)。自身の運営するオンラインメンタルジムは10年で1000名以上が受講。「曖昧さを排除した具体的な言語化」に定評がある。
YouTube: 池田潤のYouTubeチャンネル
公式note: 池田潤のnote
詳細実績: a href=”https://ike-jun.jp/profile”>池田潤の詳しいプロフィール・著書一覧はこちら】